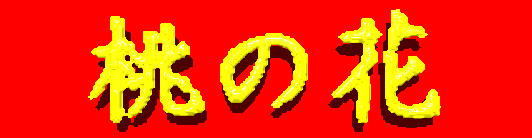
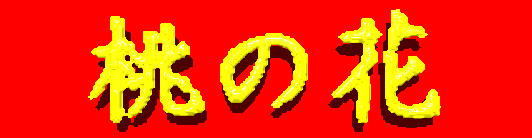
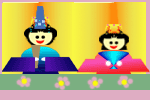
川崎市宮前区馬絹(まぎぬ)地区は、古くは江戸時代より花桃や花梅を中心とした
枝物の室(むろ)促成栽培が行われてきました。室とは、関東ローム層の地質を利用したもので、
地下に横穴を堀り、その中で麦ヌカに水を打ち発酵させ一定の温度と湿度を保った暗室で、
この中に枝物を入れ数日間蒸します。しかし現在では丘室といいブロックやパネルでつくった
ものが主流です。
現在では、馬絹花卉部会として、20軒ほどの生産者が頑張っています。春から秋は露地の切花や
枝物を出荷し、冬は室での花桃・花梅・桜・ハクレン・レンギョウなどの蒸し物を中心に出荷しています。
特に花桃の収穫時期には、毎年のようにNHKをはじめとしたテレビや新聞各紙で報道されています。
| 1 |  |
前回の伐採から丸2年たった枝です。 これを台木より切ります 枝を1m20cmから1m30cm位の長さに切ります これを そくる といいます |
| 2 |  |
枝の切り方は台木を残し、ぼうずに切ります 来年は切らずに再来年また切ります |
| 3 |  |
切った枝は4本位ずつ 畳に使うイ草で枝を よせます。これを、しおる といいます 最近では機械で、しおるのもあります |
| 4 |  |
しおった枝を20入りの束にして仕上げます そして水に、しばらくつけておきます |
| 5 |  |
この時点での蕾は、まだ硬いです この20入りの束を 室(むろ)へ何日か 入れておきます 室とは熱源を入れた暗室のことで、温度は 23度から25度に保たれ、湿度は高くなっています |
| 6 |  |
何日か経ち、3分から4分咲きになった頃、室から 出します 写真は室から出したところです |
| 7 |  |
アップで見たものです |
| 8 | 最後にビニールや箱 に梱包します これで市場への出荷の状態です |